『おしいれのぼうけん』をつくった人たち
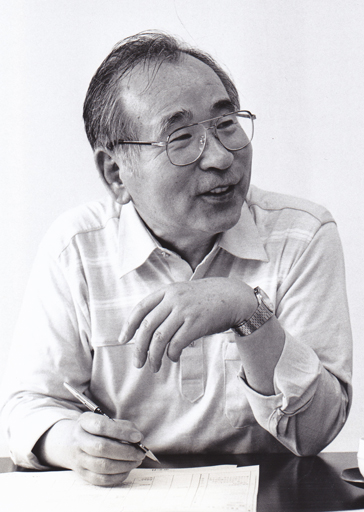
撮影・伊藤英治
古田足日ふるたたるひ
-
「絵本・ぼくたちこどもだ」の出発
ぼくたちはこの絵本で三つのことをねらいました。 その第一は子どもそのもの、それも現在の子どもをかこうとしたことです。第二は絵本でなければならないものをつくろうとしたことです。第三には、多数の子どもに喜ばれるものをつくろうとしました。
文章で物語をつくっているときのぼくの手ごたえは、その第一のことでした。幼い子どもはよく汗をかくものです。この物語中の子どもは汗ぐっしょりになって、トンネルと高速道路を走り、汗だらけの手をにぎりあいます。
第二の、絵本でなければならないものということですが、文章によって完成した短編に絵をつけるという絵本があります。こうした絵本にも存在価値は十分ありますが、ぼくたちがやろうとしたのはそれではなく、絵が語れるところは絵にまかせるということと、文と絵が一体になって独自の効果を発揮する、そして一つの場面の絵と文の一致などでした。
第三の、多数の子どもに喜ばれるものということ。これは少数の子どもに喜ばれるものより多数に喜ばれる方に価値があるということではありません。
ただぼくは、この物語を書き進めているうちに、15年間子どもの読物を書いてきた者として、これは多数の子どもに喜ばれるにちがいないと感じとりました。おしいれに入れられたあとのユーモラスな抵抗、それから汗だらけの逃走と対決、いわゆるドラマがここにあるからです。この感じは文章原稿完成後、保育園の先生やおかあさんたちが子どもの反応をたしかめてくれたあと、もっとたしかなものとなり、田畑さんの絵を見たときには90%の確信となりました。
- プロフィール
-
1927 年愛媛県生まれ。1953年、早大童話会にて鳥越信、山中恒らと共に「『少年文学』の旗の下に!」を発表し、評論と創作の双方から現代児童文学を牽引する。1997年度から2001年度まで日本児童文学者協会会長を務める。主な作品に『おしいれのぼうけん』、『ダンプえんちょうやっつけた』(いずれも童心社)、『ロボット・カミイ』(福音館書店)、『モグラ原っぱのなかまたち』(あかね書房)など多数。追悼文集『古田足日さんからのバトン』(かもがわ出版)からは、仕事の幅の広さを知ることができる。

田畑精一たばたせいいち
-
ほんとうよりもっとほんとうの
保育園のことを考えるとき、僕は丸の内のモダンなビル街のイメージを浮かべることにしています。とてもとっぴなようですが、それはこんなわけです。
ある日、僕は丸の内のビルの谷間を歩いていました。ここいく年かのうちに、このあたりのビルもすっかり新しくなったのですが、ちょうど新築したての大きい銀行の前に立ったとき、僕はほんとに恐しくて、鳥肌立ってしまいました。そびえ立つ銀行の建物は、暗く底光りする金属の壁面ですっかりおおわれて、圧倒的な威厳をもって僕を拒絶していました。とても人間が作った人間の建物とは思えませんでした。
一方の保育園のほうはこうです。密集した小さな住宅や団地に隣接して、低いフェンスにかこまれた小さな運動場、数十人の子ども達が自由に動きあそぶにはそれは全く不十分な広さです。建物はたいていもうくたびれていて、穴があいたりしているスリッパをはいて中に入ると、ワッと子ども達の歓声、笑い声、叫び声、いろんなほうむいてる机、ちらばった椅子、紙の切れはし、ボールにつみき、だいぶよごれたお人形、空カン、空びん、カメやドジョウのいる水槽、なんの芽か、芽を出したアイスクリームの容器、そして、ジーパンはいてる先生、ミニスカートの先生、いつもにこやかに笑ってる先生、ちょっとつかれてる先生。この熱気と混沌にみちみちた、保育園の姿を、あの丸の内の銀行の姿と重ね合わせたとき、ほんとうよりもさらにほんとうの保育園が僕には見えてくるように思えるのです。
- プロフィール
-
1931 年大阪市生まれ。京都大学中退後、本格的に人形劇にうちこむ。人形劇団プーク・劇団人形座などで活動の後、古田足日と出会い、子どもの本の仕事をはじめる。主な作品に『おしいれのぼうけん』、『ダンプえんちょうやっつけた』、『ゆうちゃんのゆうは?』『ひ・み・つ』(いずれも童心社)、『さっちゃんのまほうのて』、『ピカピカ』(いずれも偕成社)などロングセラー多数。「日・中・韓平和絵本」シリーズ(童心社)の呼びかけ人のひとりであり、自身は『さくら』を手がけた。紙芝居も数多く、『おとうさん』(童心社)で高橋五山賞画家賞受賞。追悼エッセイ集に『ありがとう絵本作家・田畑精一の歩いた道』がある。

酒井京子さかいきょうこ
-
子どもたちに、生きる勇気を
あげることができたら約38年前、1974年11月に『おしいれのぼうけん』は、刊行されました。そして、毎年増刷を重ね、現在では発行部数240 万部となっています。
しかし、発行当時、まさかこのようなロングセラーになるとは、だれも思いませんでした。
村松社長(当時)が、「この本は素晴らしい!10万部は売りたい!」と言った時、著者の古田・田畑先生は、「本づくりに手ごたえはあったけれど、そんなに売れるかしら?」と、おっしゃったくらいです。
増刷するたびに、また子ども読者が胸を震わせて読み聞かせしてもらう姿を見るたびに、私は、この本が子どもの心に深く入り込んでいることを知りました。しかしそれは、なぜなのでしょう?ねずみばあさんの怖さとそれと闘いぬく、主人公さとしとあきらの勇気ではないかと思います。そして、ねずみばあさんの怖さこそ、複雑で多様化する現代そのものであり、子どもたち、いいえ人間がもっている"不安"と心の奥底で呼応するのではないかと考えるようになりました。つまり、『おしいれのぼうけん』は、生きることの原点を書いた絵本でもあるのだと思います。
これからも、子どもたちに、『おしいれのぼうけん』をとおして、生きる勇気をあげることができたら、そして、本当の読書の素晴らしさを知ってもらうことができたら、どんなに素敵なことでしょう。
- プロフィール
-
1946年千葉県生まれ。1969年童心社入社。以降、編集者として紙芝居と絵本の編集に携わる。編集した絵本に「14ひきのシリーズ」(いわむらかずお・さく)、『びゅんびゅんごまがまわったら』(宮川ひろ・作 林明子・絵)、紙芝居に「ロボット・カミイ」[全4巻](古田足日・脚本 田畑精一・絵)、『したきりすずめ』(松谷みよ子・脚本 堀内誠一・絵)等がある。童心社取締役編集長、代表取締役社長を経て、現在は童心社会長。2001年「紙芝居文化の会」を多くの仲間とともに創立。以来日本のみならず世界への紙芝居普及にも力を注ぐ。「紙芝居文化の会」代表。